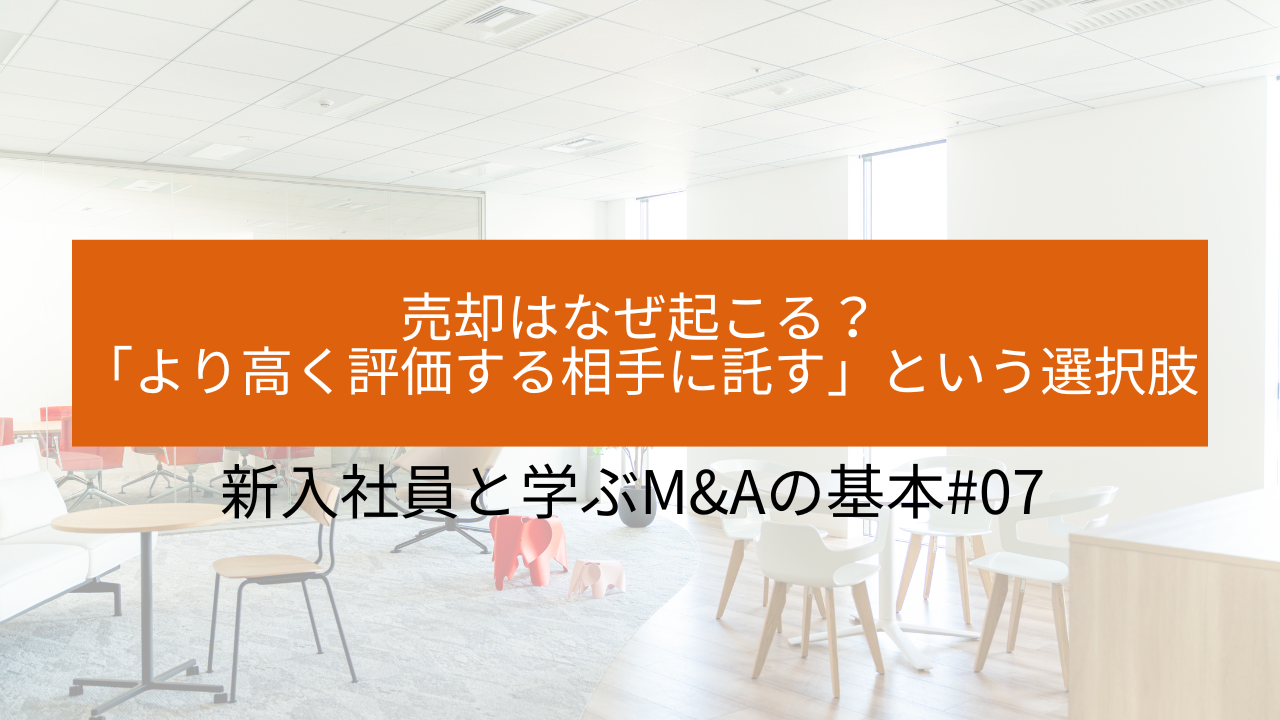
ガーディアン・アドバイザーズの事業推進チームに新たに加わった新入社員・大井。 M&Aについては、まだ学び始めたばかりです。
この連載では、そんな大井がM&A初心者代表として、CEOの佐藤に率直な疑問を一つずつ投げかけていきます。 1999年から一貫してM&Aに携わってきた佐藤の言葉を通じて、現場の視点でM&Aの基本をわかりやすく紐解いていきます。
前回は、公民の教科書にも登場する「カルテル」「トラスト」「コンツェルン」といった独占形態を取り上げ、M&Aと独占禁止法の関係について迫りました。今回は、会社を売る理由に焦点を当て、買い手とは異なる視点からその背景を学びます。
大井
以前、「なぜM&Aをするのか」を買い手の視点から伺いました。今回は売り手の視点から理由を知りたいです。
佐藤
転職の例えで話すとわかりやすいかもしれない。経営者や株主にとって、会社は単なる資産ではなく、長年ともに歩み、育ててきた一つの人格のようなもの。その会社を、今の環境よりも大きな可能性を見出せて、より高く評価してくれる相手に託すという選択を考えることがある。それはビジネスパーソンが、自分の能力をより活かせる職場へと転職し、新しいステージで成長を続けるようなもの。
大井
なるほど、会社が新しい環境で成長を続けるというイメージですね。
佐藤
そう。私がM&Aに携わりはじめた当時は、売却という言葉にはどこかネガティブな響きがあり、慎重に使わざるを得ない雰囲気があった。証券会社のM&Aアドバイザリー部門も、当時は「M&A」を冠さず、「企業情報部」などの名称で機能を持つことが多かった。しかし、今は状況が大きく変わり、事業承継やポートフォリオの整理といった前向きな文脈で語られることが増えている。
売却は「困ったときの最後の手段」ではなく、「より高く評価してくれる相手に譲る」という合理的で前向きな選択になり得る。
前向きな売却に至る背景には、大きく3つのパターンがある。
1つ目は、成長のための売却。自社の力だけでは十分に拡大できない領域へ進むため、より大きな経営基盤を持つ株主に託すケース。新たな株主をパートナーとして会社は事業の可能性を広げることができる。
2つ目は、いわゆる選択と集中で、大企業などが経営資源を中核事業に集中させるため、非中核領域を譲り渡すケース。カーブアウトと呼んだりする。残す事業も譲り渡す事業も成長させられることになる。たとえば日立は長年にわたり多様な事業を整理・売却し、株価は堅調に推移している。カーブアウトの対象となった事業が数年で単独企業として上場したりすることも多い。
そして3つ目は、事業承継を目的とするケース。オーナーが高齢になったり、世代交代のタイミングを迎えたりした際に、外部に託すことがある。近年ではプライベート・エクイティ・ファンド(PE)が関与し、社長に一定期間残ってもらったり、後継体制を整えたりしながら、海外展開を進める事例も増えている。
いずれのケースにも共通するのは、売却後の会社の成長を願っているということ。
そして、このような前向きな売却が実現するかどうかは、2つの条件にかかっている。1つは、その会社をより高く評価してくれる相手が存在するかどうか。もう1つは、その相手とのタイミングが合うかどうか。この2つの条件がそろったときに、初めて売却は実行される。
大井
背景と、実際に成立する条件とは分けて考えなければいけないのですね。
佐藤
その通り。売却は終着点ではなく、次の持ち主に託すという選択。ビジネスマンが転職によって新しいステージに進んでいくように、会社もまた、新しい環境で成長と価値を生み続けることができる。
次回は、実際にM&Aはどのように進むのか、プロセスの裏側に迫ります。
