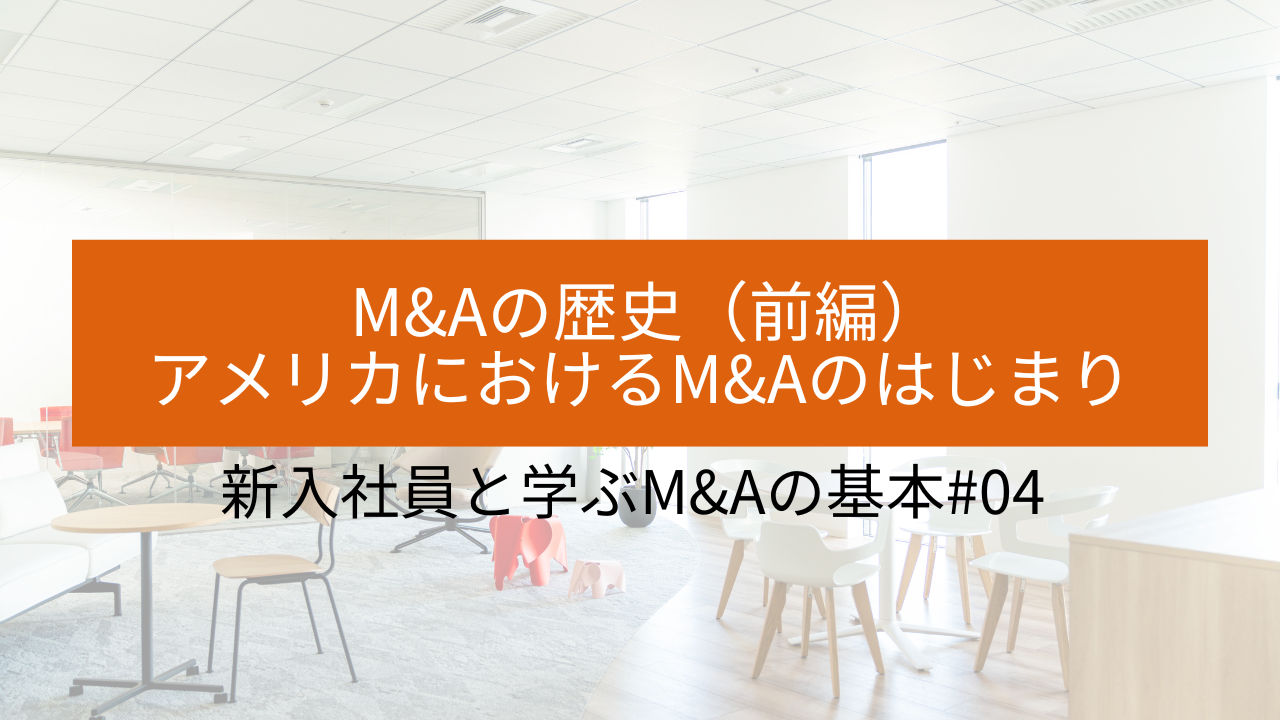
ガーディアン・アドバイザーズの事業推進チームに新たに加わった新入社員・大井。 M&Aについては、まだ学び始めたばかりです。
この連載では、そんな大井がM&A初心者代表として、CEOの佐藤に率直な疑問を一つずつ投げかけていきます。 1999年から一貫してM&Aに携わってきた佐藤の言葉を通じて、現場の視点でM&Aの基本をわかりやすく紐解いていきます。
前回は「なぜ合併・買収を行うのか?」という問いを踏まえ環境変化への適応、そして買収後の統合における「文化」という観点から解説しました。今回は、「M&Aの歴史と規制の変遷」をテーマにお届けします。
大井
M&Aは、いつ頃から始まったのですか?
佐藤
実はアメリカでは、1860年代にはすでに本格的な買収合戦が始まっていたという記録が残っている。
大井
そんなに昔からあるのですね。もっと最近のことかと思っていました!
佐藤
アメリカの伝説的なバンカー、ブルース・ワッサースタインの著書によると、1860年代に実業家コーネリアス・ヴァンダービルトが、エリー鉄道の買収を仕掛けたのが有名な話。当時はニューヨーク・セントラル鉄道やハドソンリバー鉄道など、鉄道会社が買収や合併を繰り返し、路線を急速に拡大していった時代だった。
大井
鉄道が発達していく時代に、すでに買収合戦があったのですね。
佐藤
当時は法律がまだ十分に整備されていなくて、株の買い占めや賄賂が横行していた。取締役会で承認を得るために、かなり強引な手段が取られることもあったそう。
今は当時にくらべれば、相当きちんとしたルールがある。日本だと会社法で合併の手続きが定められていたり、上場企業であれば金融商品取引法で株式取得に際して公開買付けが定められていたりする。市場の独占につながる場合は、独占禁止法によって取引が制限されることもある。
金融業界にも歴史的に規制の波があって、例えばアメリカでは世界恐慌後に投資銀行と普通銀行を分けなければならないという法律が制定された。けれど1990年代に入ると、投資銀行と普通銀行を分けなくてもよい方向に転換した。ところが、2008年のリーマンショックで金融業界が大混乱し、再び規制が強化された。
大井
規制したり緩めたりを繰り返しているのですね。
佐藤
そう。日本もかつて、金融グループが持株会社を設立することは認められていなかった。戦前、財閥が銀行から製造業まで幅広い事業を抱えていたのだけど、戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)が財閥解体を指示した。その結果、金融グループが持株会社を設立することが厳しく規制された。けれど、1997年に独占禁止法が改正されて、現在の三菱UFJフィナンシャル・グループのように金融機関を子会社として傘下に置く金融持株会社が生まれた。
大井
M&Aは、実は昔から存在していて、法律とともに少しずつ形を変えてきたのですね。
佐藤
そうだね。会社やM&Aのルールは、規制と緩和が振り子のように動きながら、今も進化し続けている。
次回は、日本におけるM&Aの原型を探ります。
坂本龍馬の亀山社中や、江戸から続く老舗企業の意外なつながりにも迫ります。
