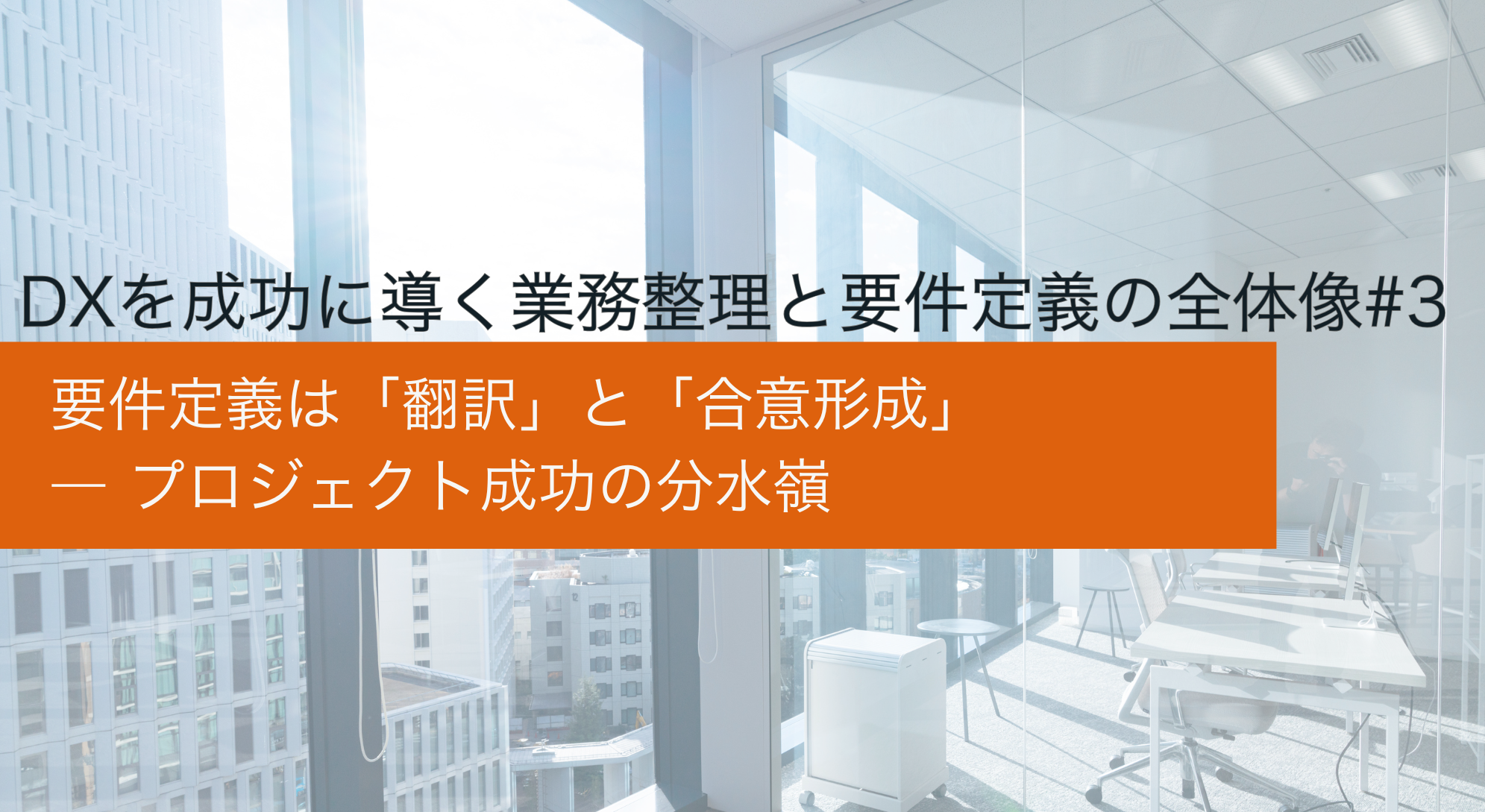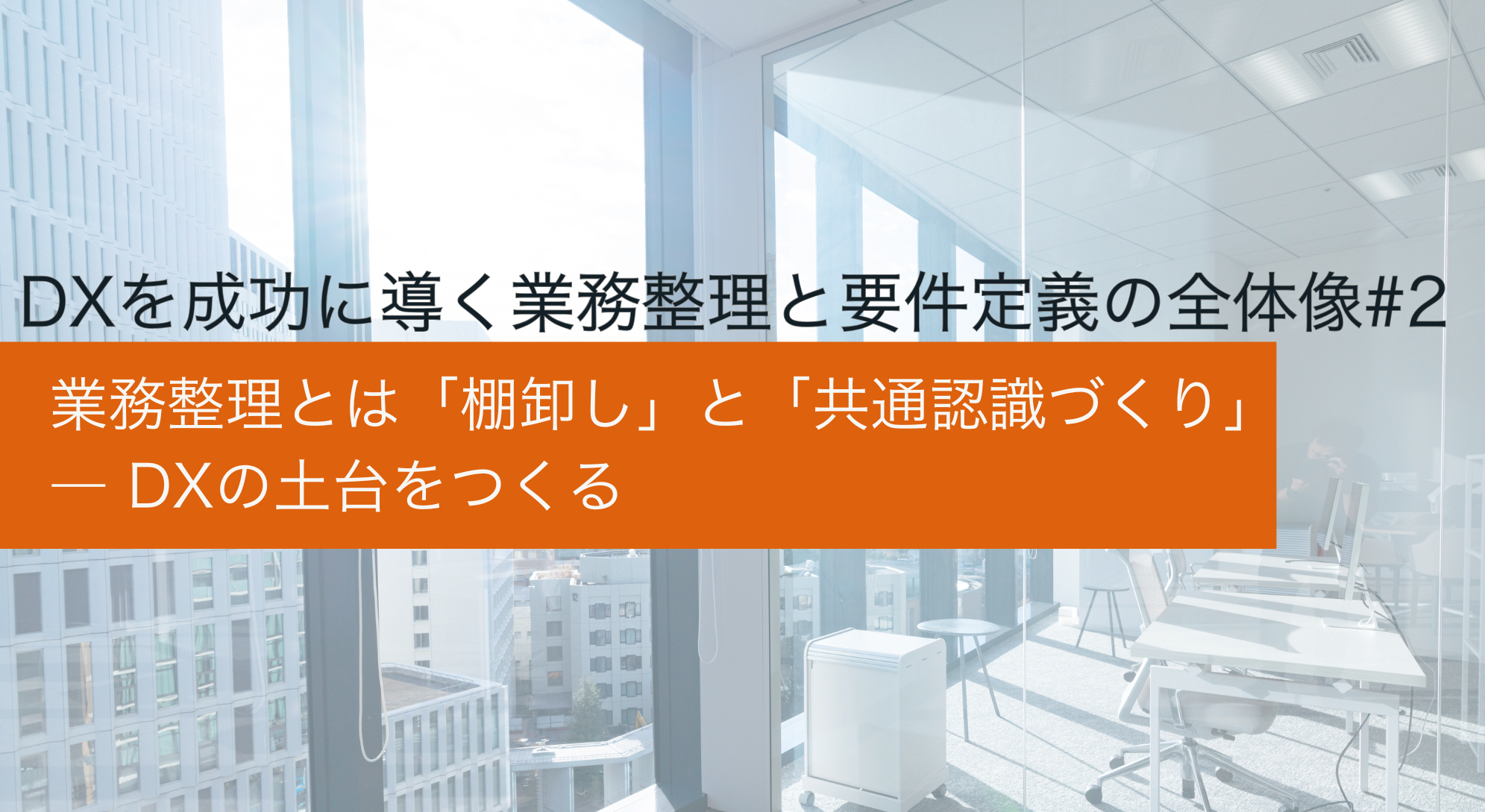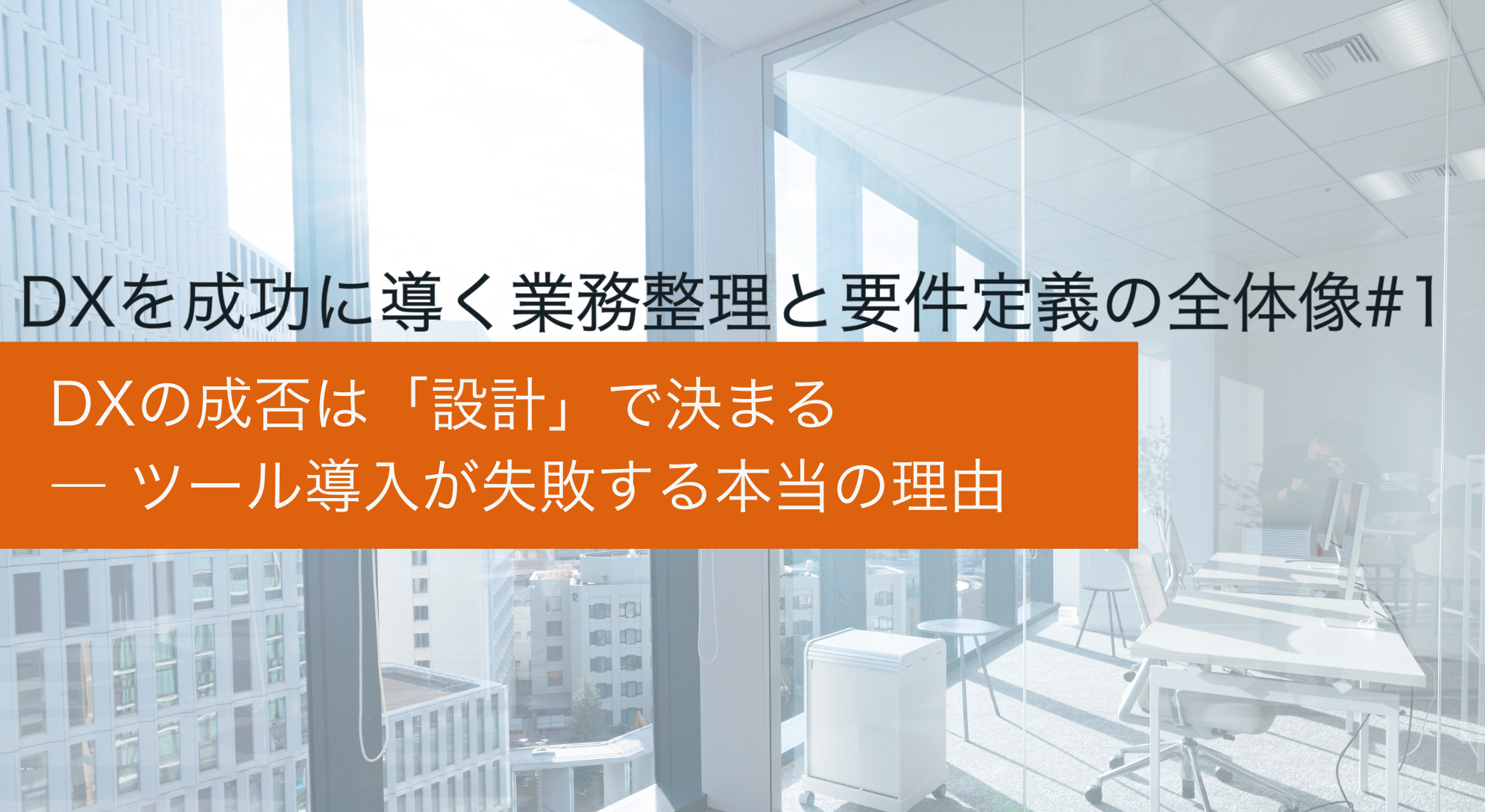#2 業務整理とは「棚卸し」と「共通認識づくり」 ― DXの土台をつくる
前回はこちら
DXを成功させる第一歩は「業務整理」です。しかし、多くの企業では“とりあえず業務フローを描くこと”が業務整理だと考えられています。確かにフローチャートを作ることで、業務の流れは視覚的にわかりやすくなりますが、そこに目的がなければ単なる図解作業で終わってしまいます。
業務整理とは、図を描くことではなく、業務の本質を理解することです。
業務整理の目的は「業務を理解すること」
業務整理のゴールは、手順を並べることではなく、「なぜこの業務が存在しているのか」を明確にすることにあります。たとえば経理部門に「請求書チェック」という業務があるとしましょう。単に「受領→入力→承認→保存」と手順を描いても意味はありません。本来の目的が「取引内容を正確に把握し、法的要件を満たすこと」であるなら、「この承認は本当に必要なのか?」「電子化による効率化は可能か?」といった改善の糸口が見えてくるのです。
As-IsとTo-Be ― 現状と理想のギャップを見える化
業務整理では、まず現状(As-Is)を正確に把握し、理想の姿(To-Be)を描くことが重要です。
ここで気をつけたいのは、“理想像”を一方的に決めないこと。経営層の目線だけで「あるべき姿」を描くと、現場とのズレが生まれ、改革が進まなくなります。理想像は、経営戦略と現場の実態の両方を踏まえて設定する必要があります。
As-IsとTo-Beを比較することで、業務のどこにムリ・ムダ・ムラがあるか、どこを変えるべきかが明確になります。
組織全体で「共通認識」をつくる
業務整理は、担当者だけの作業ではありません。部門横断で「なぜその業務をしているのか」「誰が関わっているのか」を議論し、全員が共通の理解を持つことが重要です。
このプロセスでは、経営・現場・IT部門の三者が同じテーブルで話すことがポイントです。それぞれの視点を持ち寄ることで、「この業務は他部署にも影響していたのか」「ここは連携すれば効率化できる」など、全体最適の視点が生まれます。
副次的な効果 ― 組織のコミュニケーションが変わる
業務整理のもう一つの効果は、社内コミュニケーションの活性化です。普段関わりの少ない部門同士が業務について話し合うことで、「お互いの仕事の流れを知る」「相手の課題を理解する」といった変化が起こります。業務整理は単なる業務改善ツールではなく、組織の“認識を合わせる場”でもあるのです。
業務整理はDXの“棚卸し”
倉庫の在庫を整理するように、業務整理は業務を一つひとつ棚卸しする作業です。どんな業務があり、どれが価値を生んでいて、どれが不要か。それを明確にして初めて、「次にどんな仕組みをつくるべきか」が見えてきます。
つまり、業務整理はDXのスタートラインです。この整理ができていない状態で要件定義に進むと、設計の基準があいまいになり、結果的に“現場に合わないシステム”ができあがってしまいます。
次回は、この業務整理のうえに立って進める「要件定義」について解説します。
要件定義は、単なる設計ではなく、現場とシステム部門の“翻訳”と“合意形成”のプロセスです。ここを丁寧に行えるかどうかが、プロジェクト成功の分かれ道になります。