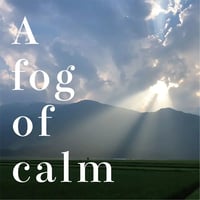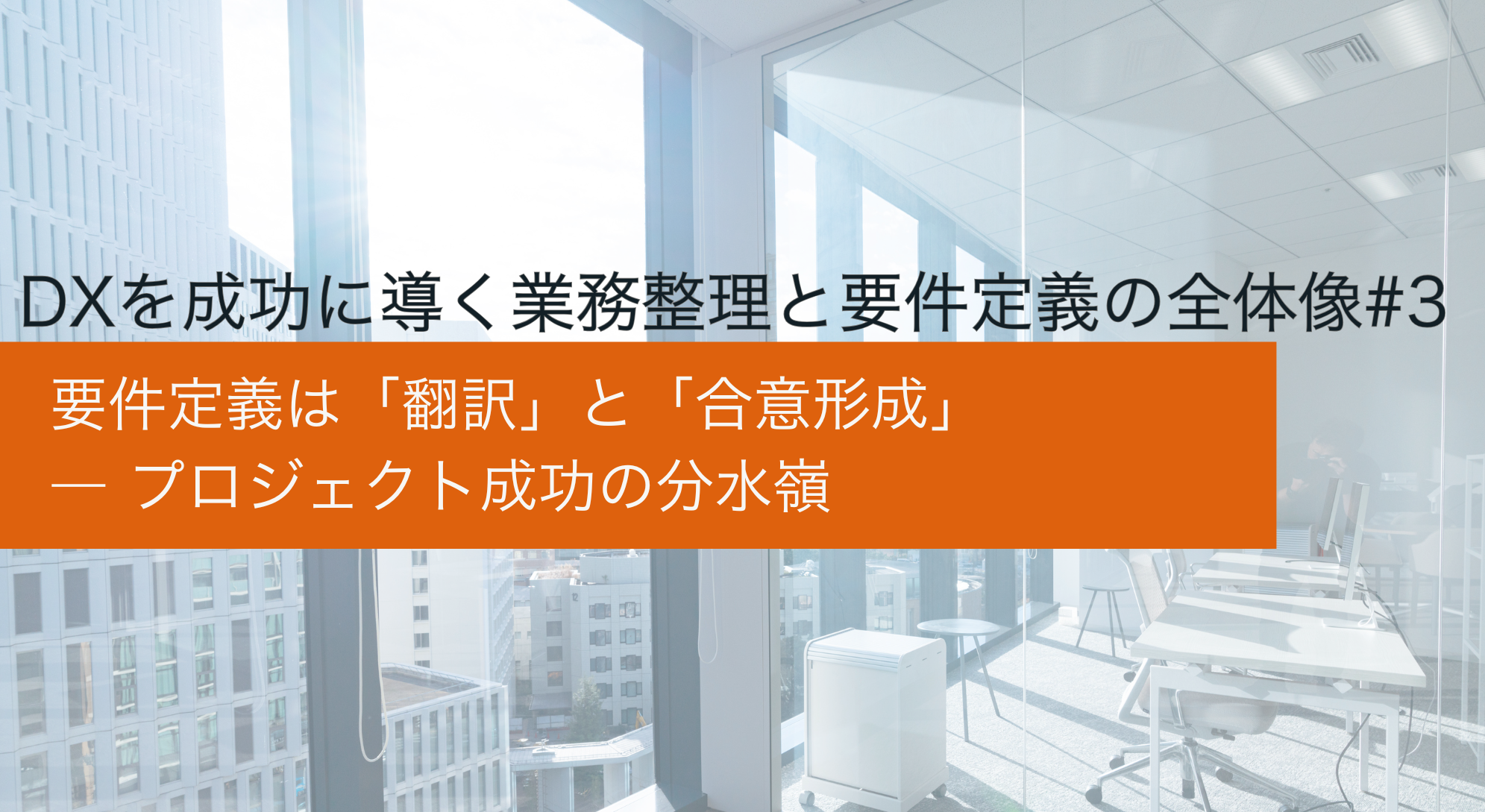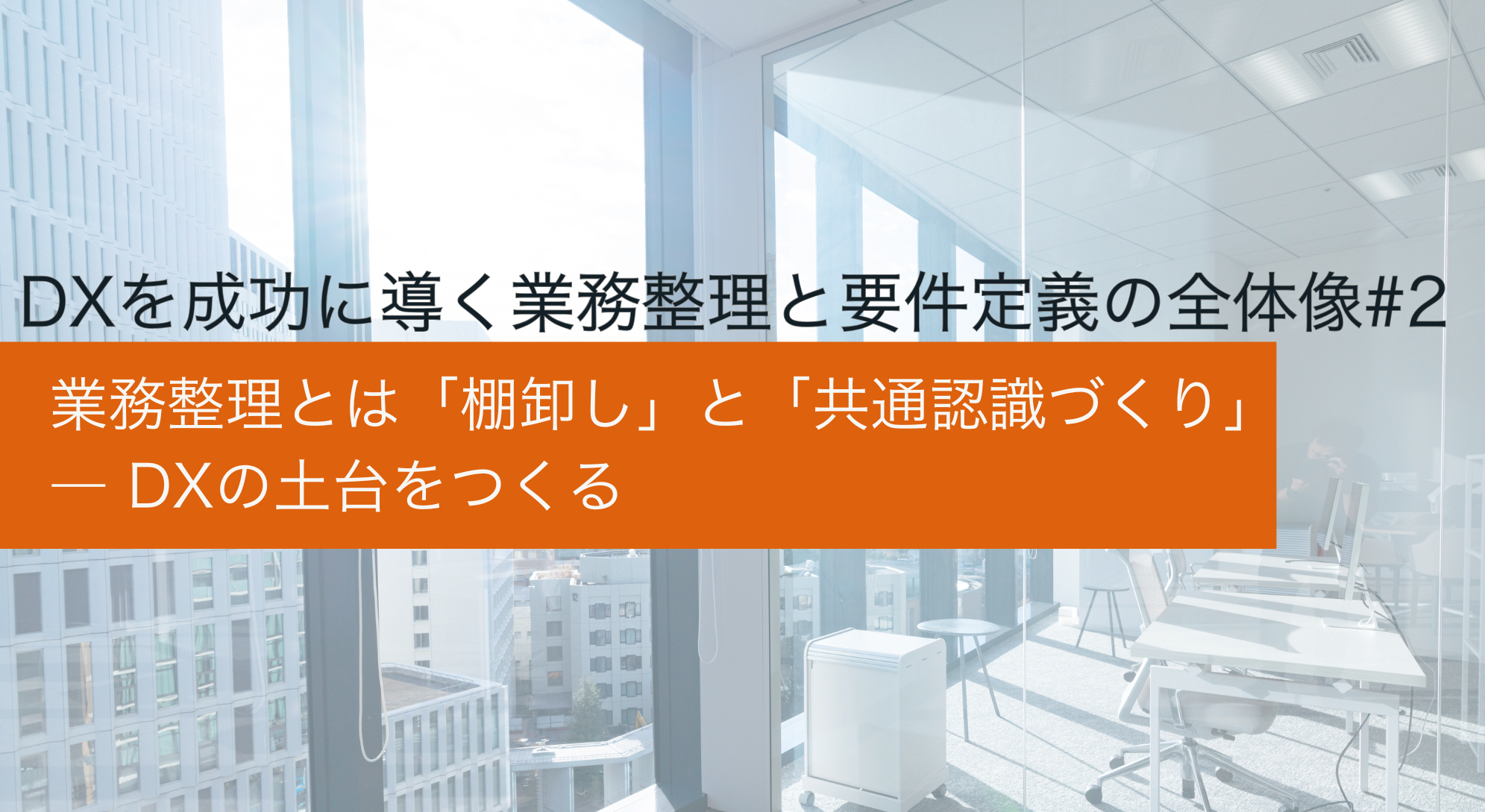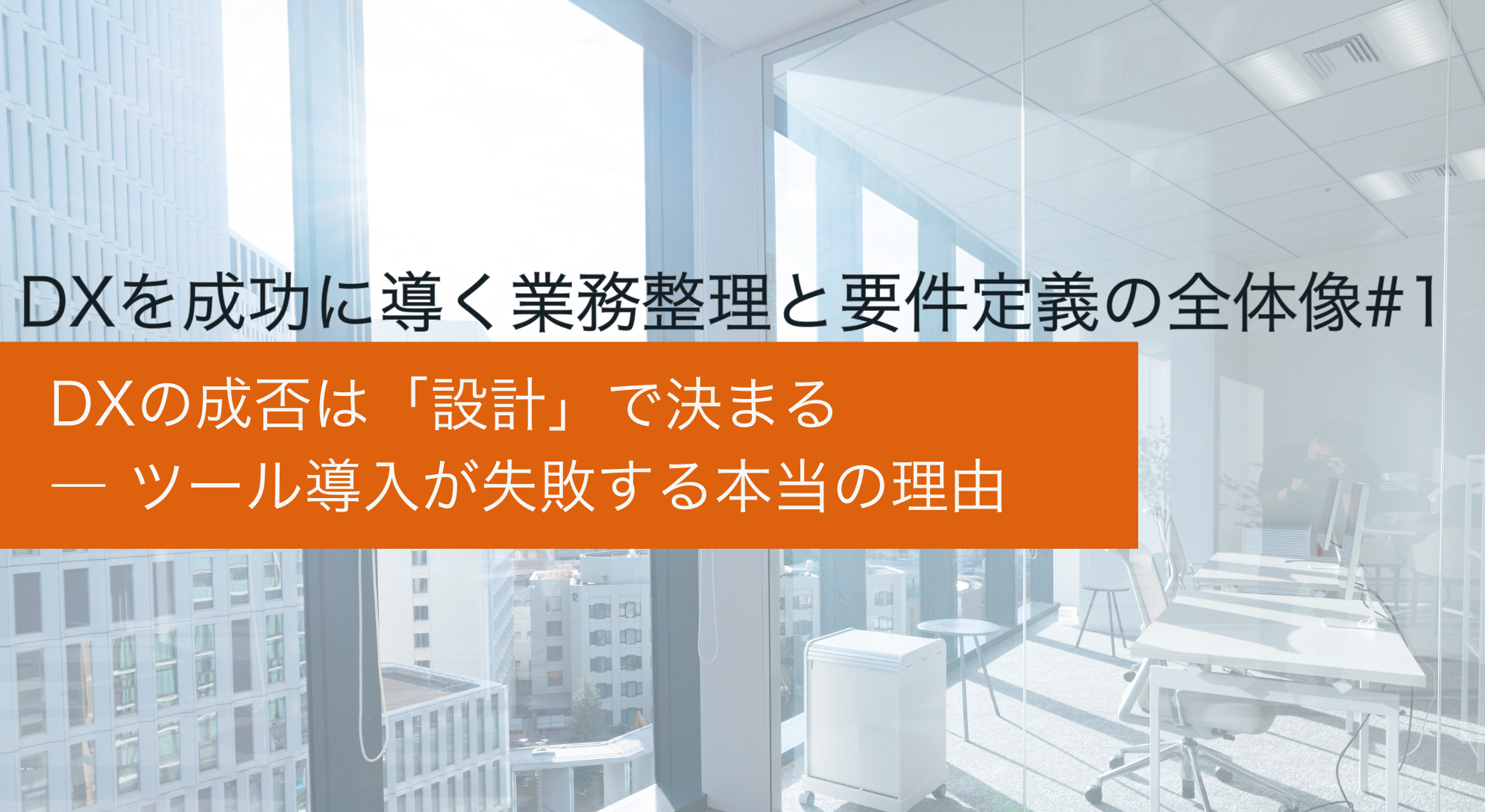NFT技術がもたらす楽曲販売の新しいカタチ
前回
は「Web3」とは何かという話をさせて頂いた。そのWeb3の概念を支える技術がNFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)
だという話をしたが、今回は、実際にNFTのスタートアップで起こっているニュースを拾ってみたいと思う。
昨年末、音楽のNFT販売プラットフォームである「Sound.xyz」がベンチャーキャピタルのAndreessen Horowitzからシードラウンドで500万ドル(約5億7000万円)の調達に成功した。この「Sound.xyz」から、年始の時点で既に数名のアーティストが楽曲を発表しておりマネタイズに成功している。
これまでのビジネスモデルでは、無名のアーティストはまず、インディーズレーベルで実績を積み、メジャーレーベルとの契約に及び、やっとそこから本格的なキャリアをスタートするのが常だった。いわゆる事務所と呼ばれるメジャーレーベルは、アーティストを更に磨くために投資を行い、これを最大化していく、一大産業だった。
しかし、かつてポストしたように、楽器そのものがデジタル化することで楽曲制作からマネタイズのプロセスまでもが大衆化した。典型的にはDTM(Desktop Music)が一般化し、マンションの1室でフルオーケストレーションの曲を作成しメディアにするところまで、1人で出来るようになった。
となれば、次はこれを世界中に届けるプラットフォームの存在が待たれる。
Appleはパソコン屋としてそのキャッシュポイントを増やすべく
、
iTunes
や
AppleMusic
をスタートしたし、Amazomも同じようなサービスをとっくにリリースした。
Spotify
のようなプラットフォームはデジタルネイティブが、いわゆるレコード屋に通う文化を消失させ、
SoundCloud
はアマチュアからプロまでの音楽製作者による楽曲配信のデファクトになったといっても過言では無い。
また、AppleやAmazon、またはSpotifyのような「大手」は比較的、これまでの「メジャーレーベル」に所属するアーティストの楽曲をクラウド配信に「置き換える」プラットフォーマーだったが、一方で無名の音楽家は前出のSoundCloudや
TuneCore
などのサービスを使い、全世界に自分の音楽を配信することで、その再生回数やダウンロード回数によって音楽製作者は収入を得られる様になった。実は私も作曲家として今年で27年も活動を続けており、かつて作曲した楽曲を1回限りで企業に買ってもらうことで成立していたマネタイズは、TuneCoreなどの出現で
ロングテール
へと移行し、その毎月の収入は個人的な収入のポートフォリオの中でも存在感を放つまでになった。
さて、ここまで書いてきたことは、技術としてのNFTとは無縁の世界である。つまり「もう既にこの状態で完成されているではないか」という指摘はアンチNFT論者から日々日々飛んできている。
しかし、
前回のWeb3の議論
にもあったように、ビックデータや中央集権的なサービスにアンチの立場をとるのに適しているNFTという技術であれば、その複製の行き先は確実にトレースできるし、製作者に確実に収益は還元される。また「Sound.xyz」のサービスでは、楽曲中のその瞬間に対してコメントを残せる「ソーシャリー」な機能などがあり注目をされているが、コメントをしたその楽曲を次の人に売った際には、前の人のコメントが消えるなど、とても「NFT的な機能」も満載されていたりと、これまでの楽曲配信及びマネタイズの仕組みとは違ったNFTの良さも出てきている。
一方で、
Web3の投稿
で述べた通り、これまでのデータドリブンの支配的なサービスへの抵抗の側面が大きいといいつつも、完璧に製作者に収益などの還元をするがあまり、リミックスやカバーといった、これまでの著作権法との兼ね合いでも微妙だったが、性善説的で、民主的で、かつ自由主義的に育った文化がここでデッドエンドになるのではないかという議論もあるようだ。論文執筆も楽曲制作も、先駆者を真似るところから始まる。かつて私が有名ウェブデザイナーと仕事をしていた時、海外のとあるウェブサイトのデザインに、ものすごく心打たれたことがあった。そのサイトを制作したデザイナーにメールを書いて、デザインのどこに心打たれたか、なぜ心打たれたかを書きリスペクトをした上で、そのデザインのアイディアを拝借させて欲しいとお願いをしたところ「どんどん使ってくれ」という快い返信が戻ってきたことを思い出す。こういった、ある種、既存の法律では極めて危ない側面だが、しかし、文化や人と人とのコミュニケーションがこれをカバーしていた世界があったとすると、今後のNFT技術はこれをどうやってアップデートするのか非常に楽しみである。そういった側面を残すNFTを利用したスタートアップにAndreessen Horowitzが出資をしたという事実はとても興味深く、今後しっかりとフォローしていきたいところである。
|
ご参考: 「A fog of calm」 |
ガーディアン・アドバイザーズ株式会社 パートナー 兼 IT前提経営®アーキテクト
立教大学大学院 特任准教授
高柳寛樹
----
高柳の著書はこちらよりご参照ください。
「IT前提経営」が組織を変える デジタルネイティブと共に働く(近代科学社digital)2020
まったく新しい働き方の実践:「IT前提経営」による「地方創生」(ハーベスト社)2017
----