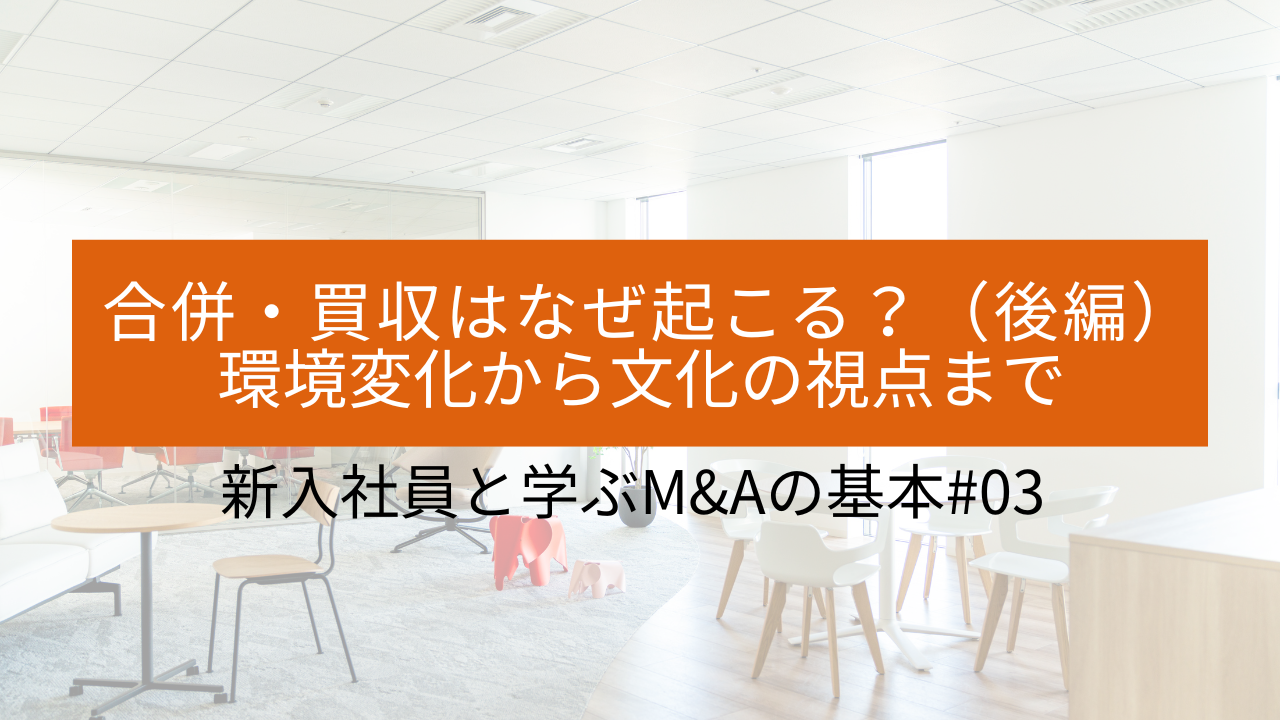
ガーディアン・アドバイザーズの事業推進チームに新たに加わった新入社員・大井。 M&Aについては、まだ学び始めたばかりです。
この連載では、そんな大井がM&A初心者代表として、CEOの佐藤に率直な疑問を一つずつ投げかけていきます。 1999年から一貫してM&Aに携わってきた佐藤の言葉を通じて、現場の視点でM&Aの基本をわかりやすく紐解いていきます。
これからM&Aに関わる可能性のある皆さんへ。 「知らなかった」が「そういうことか」に変わる、そんな一歩になれたら嬉しいです。
大井
これまでM&Aは一企業の経営判断として完結するものだと考えていましたが、日本製鉄によるUSスチール買収の話を聞いて、業界全体にも波及する影響があることを実感しました。
佐藤
大きな産業で何かが起きると、その影響は広範囲に及ぶ。たとえば、かつてルノーが日産に出資してカルロス・ゴーン氏が経営に関与するようになったとき、日産は取引先の見直しを行い、多くの会社との取引を打ち切った。取引を失うと利益を出せない会社がでてくる。そういう会社は生き残るために、新しい取引先を探したり、他の会社に買収されたりしたこともあった。当時はちょうどプライベート・エクイティ・ファンドが台頭してきた時期でもあって、ファンドが買収するケースも増えた。
大井
業界の変化に応じて、動かざるを得なくなるのですね。
佐藤
そう。企業は一見、自分たちの判断で自由に動いているように見えても、実際には環境の変化に適応しているだけ、ということも少なくない。
人口減少や気候変動、生活スタイルの変化など、世の中の環境が変わると、商売の形も変わる。そうした変化に合わせて企業が対応しようとする中で、M&Aが活用されるケースも多い。
大井
なるほど。つまり、企業がM&Aを行う背景には、外部環境の変化に対して積極的に動こうとする姿勢もあるということなんですね。
佐藤
その通りで、企業は「どうありたいか」を常に考えている。特にスピードが求められる場合は、一から事業を立ち上げるよりも、すでにその分野で事業を展開している企業を買収した方が早いことから、M&Aが有効な手段になることも多い。「M&Aは時間を買う行為」とよく言われるのは、まさにそのため。
たとえば、飲食業を営む企業がインドや東南アジアに進出したい場合、自社で1店舗目から出店するよりも、現地ですでにチェーン展開している会社を買収することで、一気に市場参入を果たすことができる。
大井
買収された会社の文化や、それまでそこで働いていた人たちの思いは、そのまま受け継がれていくものなのでしょうか? たとえば、現地で長年続けてきた営業スタイルや、従業員とお客さんの関係性といった、その会社らしさが損なわれてしまうことはないのかなと思いまして。
佐藤
そこは今、すごく重要視されている。前回、M&Aは「ビジネス・財務・法務」の3つの観点から考える必要があると伝えたけれど、それに加えて最近は「人」や「文化」の観点もとても大事だと考えられている。買収した会社の人たちと良好な関係を築き、協力体制を整えていかないと、M&Aによる価値創出は実現しにくいから。
大井
いきなり社風を変えられたら現場は大変ですよね。
佐藤
そうそう。たとえば、のんびりとした社風の会社がスピード重視の会社に買われたら、急に働き方が変わってしまうこともある。部活でいうと、文化系の部活がいきなり体育会に入れられる、みたいな感じ。
大井
それは辛いですね。
佐藤
だから最近は、買収した会社とうまくやっていけるか、そしてその文化を尊重できるかもますます重要視されている。
大井
M&Aをする際の考え方も変化しているんですね。そもそも、M&Aはいつ頃からあるのでしょうか?
次回は、「M&Aの歴史と規制の変遷」をテーマにお届けします。
19世紀アメリカの鉄道業界に始まる買収合戦から、M&Aが社会とともにどう変化してきたのかを、歴史を通して見ていきます。
