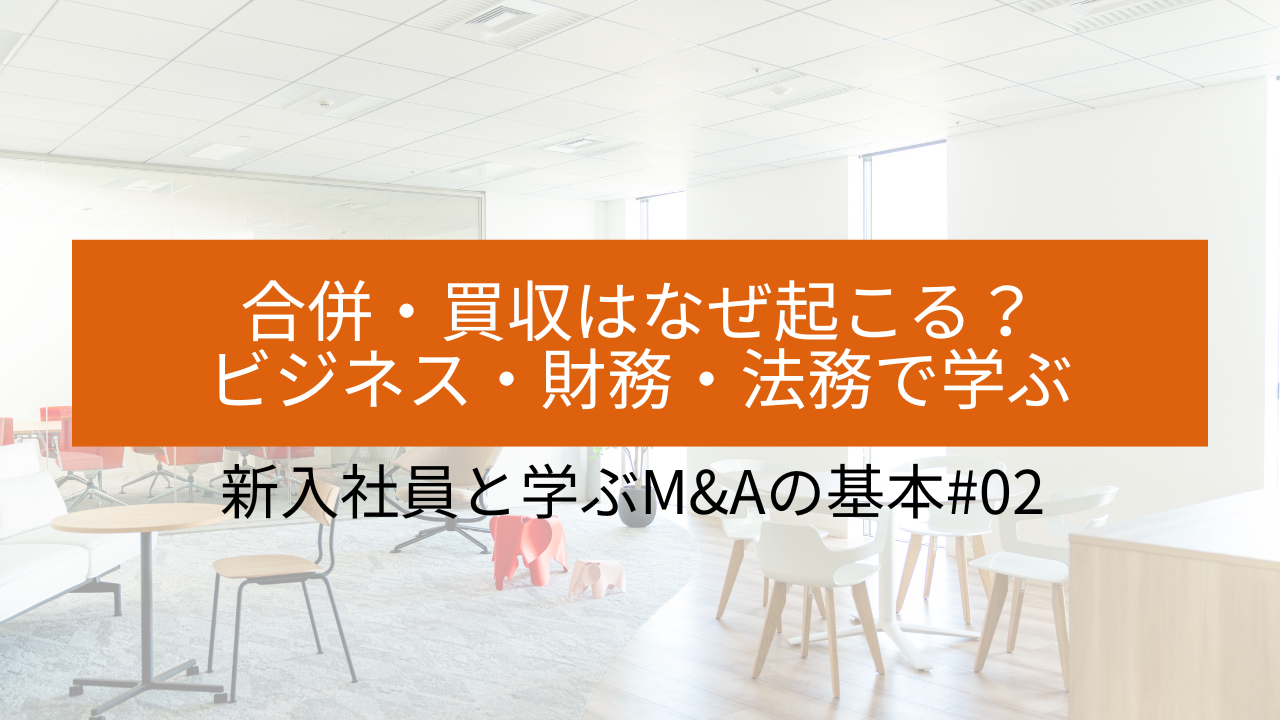
ガーディアン・アドバイザーズの事業推進チームに新たに加わった新入社員・大井。 M&Aについては、まだ学び始めたばかりです。
この連載では、そんな大井がM&A初心者代表として、CEOの佐藤に率直な疑問を一つずつ投げかけていきます。 1999年から一貫してM&Aに携わってきた佐藤の言葉を通じて、現場の視点でM&Aの基本をわかりやすく紐解いていきます。
これからM&Aに関わる可能性のある皆さんへ。 「知らなかった」が「そういうことか」に変わる、そんな一歩になれたら嬉しいです。
大井
佐藤さん、そもそも企業はなぜ会社を合併・買収するのですか?
佐藤
なぜだと思う?
大井
利益を上げるためでしょうか?
佐藤
確かにそれもひとつの目的で、ビジネスと財務の2つの観点で意味があるから。
たとえば、事業を拡大したいとか、新しい市場に入りたいとか、ビジネス上の狙いがある。さらに、財務的に合理的だとか、投資として魅力があるとか、そういう理由もある。
大井
ビジネスの観点でいうと、企業は具体的にどのような状況で買収・合併を検討し、M&Aを行うのでしょうか?
佐藤
たとえば、企業が業界の構造変化に対応するために、M&Aを選ぶことがある。
新日本製鐵と住友金属がなぜ一緒になったのかを考えてみてほしい。
鉄の原料である鉄鉱石は、鉄鉱山から採れる。その鉄鉱山を所有する資源会社が、世界中で買収を繰り返してどんどん巨大化していった。そうなると、製鉄会社が小さいままだと交渉力で完全に不利になる。つまり、資源会社の言いなりになってしまう。そこで製鉄会社も対抗するために、規模を拡大する必要があった。
日本にはかつて、4つ大きな製鉄グループがあったのだけど、世界の競合と比べると、圧倒的に規模が小さかった。だから新日本製鐵と住友金属は統合したし、最近ではアメリカのUSスチールの買収もして、さらに大きな存在へと進化している。
こういう背景からもわかるように、M&Aには戦略的な必然性がある。
大井
そうやって業界全体の動きに対応するために動くんですね。M&Aって、単なる成長手段じゃなくて、生き残るための選択肢でもあるんですね。
ビジネスの話に続いて、財務の観点ではどういう理由があるのでしょうか?
佐藤
財務の観点で言えば、当然だけど、儲かる見込みがなければ買収しない。買ったあとに業績が悪化するような会社をわざわざ買うことはない。
たとえば、プライベート・エクイティ(PE)ファンドは、財務面を重視してM&Aをしている。買収した企業の収益構造を改善して、企業価値を高めたうえで、買ったときよりも高く売ることで利益を出すモデルだから。財務的に採算が合うかどうかは、M&Aを実行するうえでの大前提になる。
大井
ビジネス上の狙いがあって、財務的にも利益が見込める。そういう両方の条件がそろってはじめてM&Aをするんですね。
佐藤
そして、もう一つ重要なのが法務。
どんなにビジネスや財務上意味があっても、実行するには法務の要件をクリアしないといけない。たとえば、上場企業の株式を一定以上買うなら公開買付(TOB)が必要だし、巨大企業同士の合併なら独占禁止法の審査を必ずクリアしないといけない。
新日本製鐵と住友金属が合併したときも、大きくなりすぎるから厳しい審査を受けた。
日本製鉄によるUSスチールの買収も、アメリカ政府の承認が必要だった。
法務のハードルを越えられなければ、どんなに良い話でも実現できない。
大井
なるほど。ビジネスと財務がM&Aをする「理由」で、法務はそれを実現するための「条件」ってことなんですね。
佐藤
そう。やりたい、儲かる、実現できる。この3つがそろってM&Aは成立する。
大井
3つの観点で分けて考えると、かなり整理されますね!
企業が環境の変化にどう対応するか。その手段のひとつが、M&Aです。
次回は、そうした「環境変化」をテーマに、M&Aが実際にどう使われているのかを、事例とともに見ていきます。
