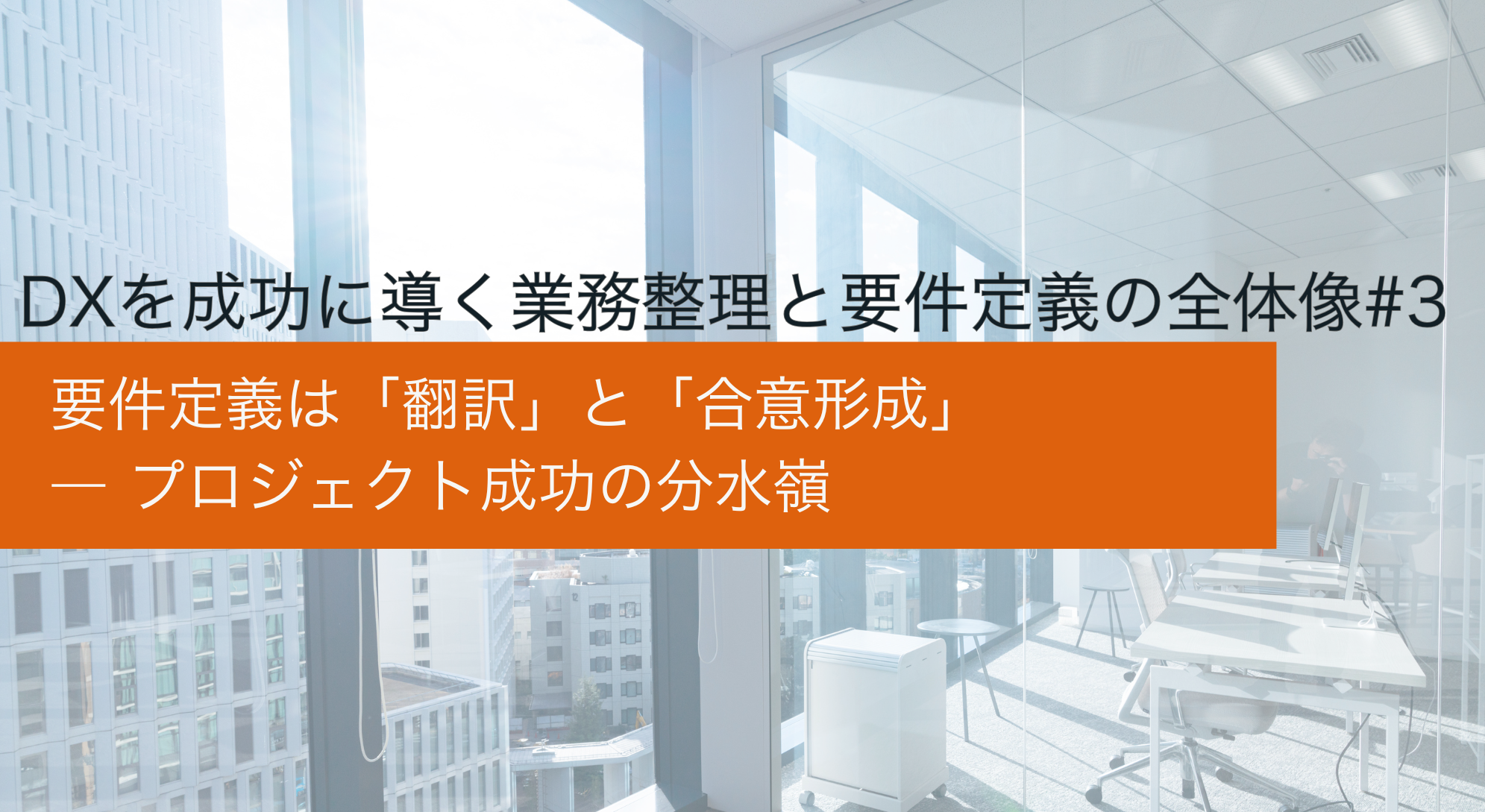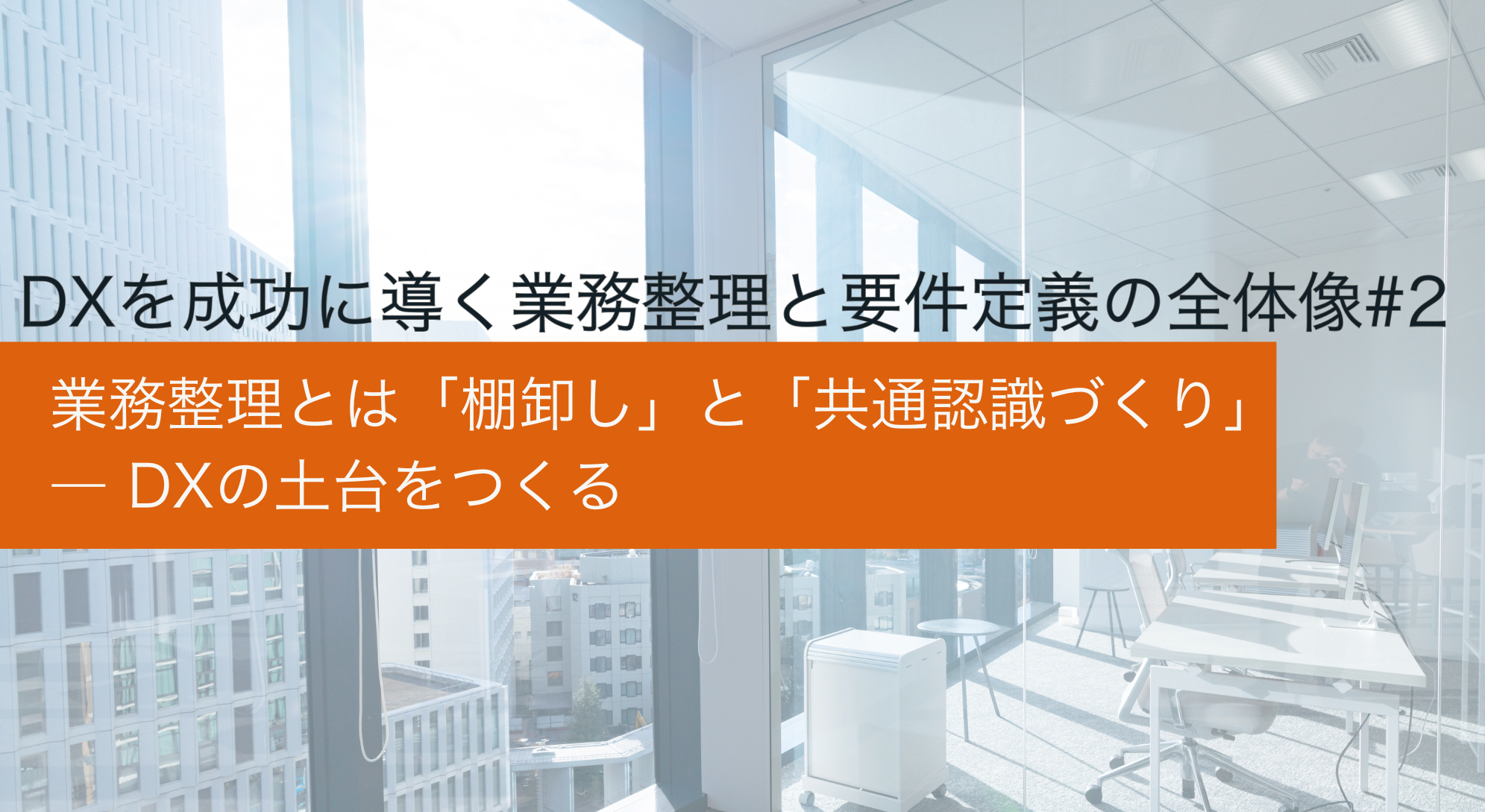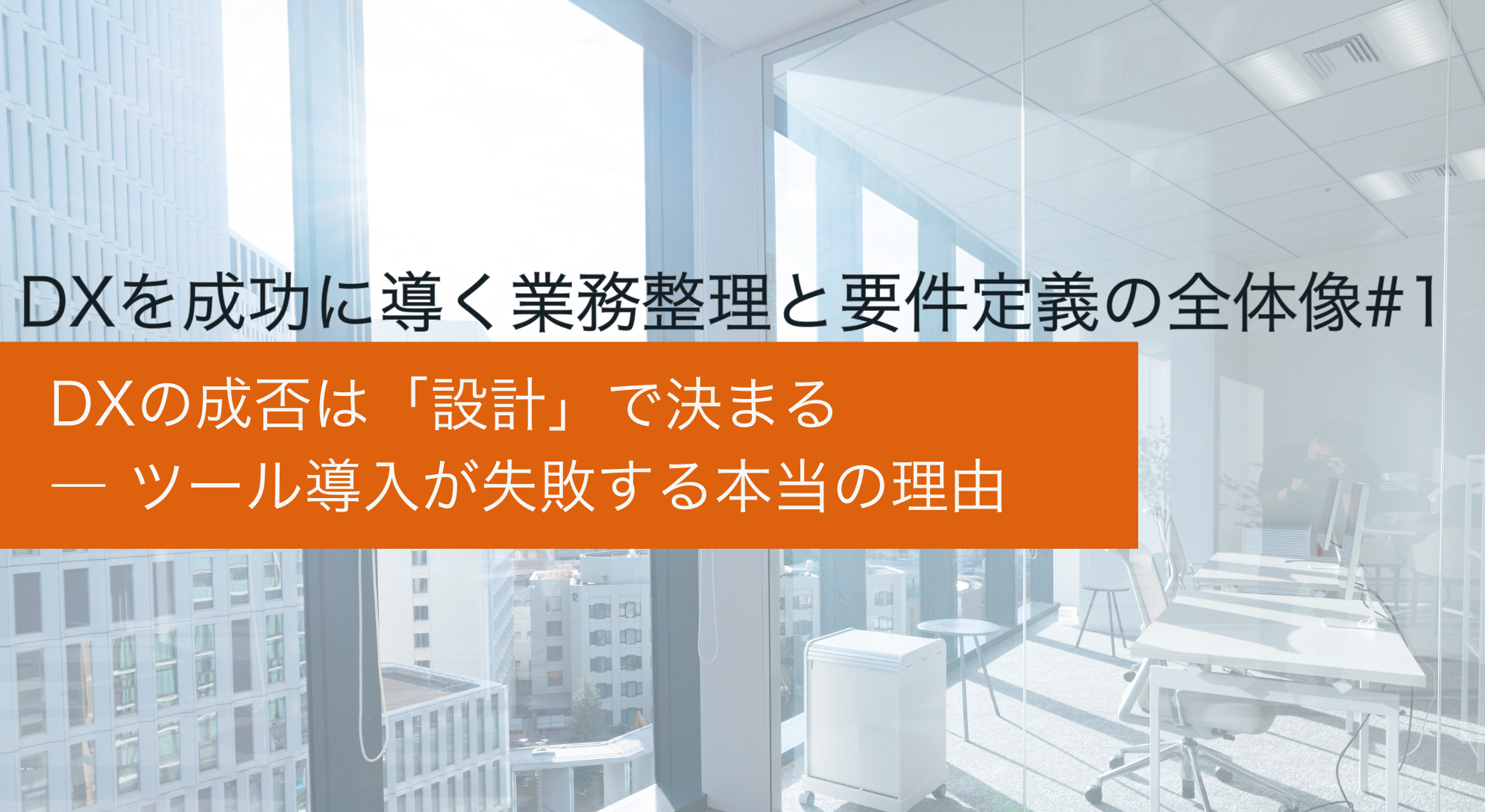オンラインはリアルに追いつけるのか。〜スピーカー視点でのwithコロナ〜
COVID-19で会議がオンラインになり、大学での授業やゼミもオンラインになりました。400名の履修者がいる大教室の講義もオンラインとなり、セミナーや講演会のほとんどはウェビナーになってしまいました。
こういう仕事を長くしていると、オーディエンスの表情を見ながら自分の話していることが受け入れられているか、理解して頂いているか、ということを汲み取りながら話の粒度を微調整していく感覚が身についています。
少人数のゼミなどでオンラインでも学生の表情を見ることができれば、ほぼ教室と同じコミュニケーションが成立しますし、同時にチャット機能も使えるので、ひょっとすると教室よりも良い授業が提供できている可能性はありますが、
問題は数百名の大講義とウェビナーです。
講義形式の場合は、学生が顔を出さないことが多いです。
顔を出すことを強制すると一種のハラスメントになるとかならないとかという議論もありますが、そもそも、
400
名のオンライン講義で顔を出されても意味がありません。
質問の時だけカメラをオンにするのはなんとなく自然発生的な「優しさ」になっていますが、基本はオフです。
これはウェビナーも一緒です。
先日も
No Making, Just Using
に関するウェビナーをやり、数百名の方に参加して頂いているとわかってはいるものの、基本的には
PC
や
iPad
に向かってスライドを送りながら喋り続けるという苦行です。
よく「壁に向かって喋っている」と言いますが、前述した通り、オーディエンスの表情を見ながら話す内容を微調整する側からすればウェビナーはかなりやり辛いのです。
しかし、これは今に始まったことではないことに気づきます。
よくよく考えると、テレビのキャスターやアナウンサー、そしてラジオのパーソナリティーは、ずーっとこれです。カメラやマイクに向かって喋り続ける訳です。
ラジオの方がリスナーに伝わる情報量が少ないから、「伝える力」は必要かもしれません。
では、ウェビナーや
400
名規模の講義で、どうやったら「壁に向かって話している」感がなくなるのか。
それは聞き手の配置だと思っています。
ラジオでもパーソナリティーとアナウンサーといった組み方の番組は多いですよね。
相槌をうってもらうだけでもだいぶ違います。
私みたいな大学教員も
100
分の授業でずっと喋っているよりは、ゲストスピーカーなどにご協力頂き、
2
人のディスカッションを学生に聞いてもらうようにした方が、聞く方も話す方も圧倒的に進めやすいし、わかりやすいコンテンツになります。
かつて、「ラジオデイズ」プロデューサーの平川克美さんが、「ラジオはコタツで収録でき
るからいい」とおっしゃったのは、まさにこのことです。
相槌だけでも全然違うので、最近は授業に
TA
(
Teaching Assistant
)をつけて、相槌をお願いしたりもします。
これはラジオに倣ってやり始めたのですが、私の負荷も軽減されると同時に学生からも質問や議論を引き出せます。
COVID-19
の
1
年目に、大学だけではなく高校でもオンライン授業やオンデマンド授業をデリバリーしなくてはいけなくなり、特に高校のオンデマンド授業では、友人の専門家や先生方にご協力いただき、「話し相手」になって頂いて、
2
人の「会話」を収録して授業としてデリバリーしました。
ちょっとした工夫ですが、ウェビナーを楽しくする方法は色々あると思っています。
このブログも
2
人の会話形式のポッドキャストにした方がいいなと前から思っています。
準備ができたらチャレンジしても良いかもしれません。
ガーディアン・アドバイザーズ株式会社 パートナー 兼 IT 前提経営®アーキテクト
立教大学大学院 特任准教授
----
弊社支援の事例をまとめた資料については弊社の IT 前提経営 ®︎ アドバイザリーページ よりダウンロード頂けます。
高柳の著書はこちらよりご参照ください。
「 IT 前提経営」が組織を変える デジタルネイティブと共に働く (近代科学社 digital ) 2020
まったく新しい働き方の実践 : 「 IT 前提経営」による「地方創生」 (ハーベスト社) 2017
----